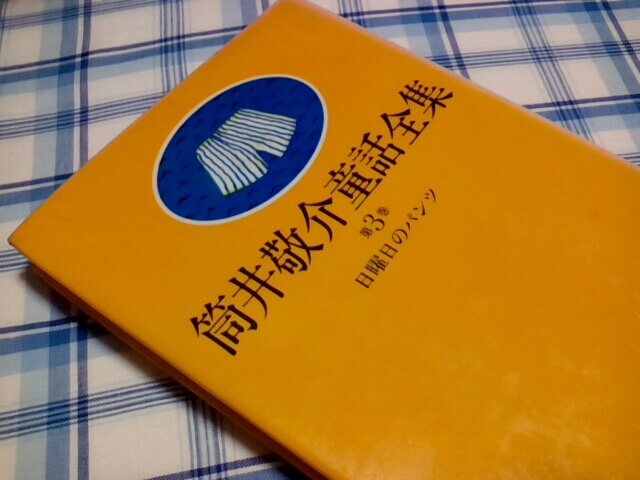
こんにちは。「コロッケ町のぼく」というお話をご存知の方ってどのくらいいるのでしょうか?
多分そんなに多くないと思うのです。
と、言いますか私はこのお話のタイトルすらちゃんと覚えていませんでした。
覚えていたのはこの話に出てきたコロッケの話です。
主人公の僕は町のお肉屋さんのコロッケが大好きなのです。
ここのコロッケはくず肉じゃなくてちゃんとしたお肉をコロッケに入れているというのがその理由です。
他のコロッケというのは、骨についてる筋みたいなのを削り取ってミンチにしたようなくず肉を使っているのであまんまり美味しくないんだって語っていたのです。
小さいころにこの話を読んだ私は、このコロッケが美味しそうでおいしそうでたまらなかったのです。もう強烈にこのコロッケの肉の話が脳裏にこびりついているせいで、お惣菜として売っているコロッケを見るたびに「このコロッケはちゃんとした肉を使っているのだろうか?それとも骨のすじ肉をこそぎとったくず肉だろうか」って考えてしまう癖がついています。
このコロッケが出てくる話をもう一度読みたいと思ってかすかな記憶を頼りに探してみました。
それが「コロッケ町のぼく」という作品です。
強烈に覚えているのはコロッケのシーン
小さい頃に読んだ本の美味しそうな物って強烈に心に残ってはいませんか?あっ、本に限らないですね。アルプスの少女ハイジが食べてたヤギのチーズの火にあぶられてとろーってなるところとか本当にたまりません。
前に話題に出した、大草原の小さな家シリーズのローラの話、大きな森の小さな家に出てくる食べ物の数々は本当によだれが垂れそうなほど美味しそうでした。
ぐりとぐらのパンケーキとかからすのパン屋さんの見開きいっぱいのパンとか、思い返せば本の中には美味しそうな物がたくさんあります。
そんな本の中の美味しそうなものの中でも、私が何故か強烈に覚えているのがコロッケなのです。
お話のあらすじとか前後がどんな感じだったのかまったく思い出せないのに、狐色のコロッケがさくっとしていてじゅーしーで肉がうまくて立ち食い最高!って感じの印象がはっきりきっぱり残っています。
そう、肉が美味いコロッケなのです。本当にそこだけ妙に覚えているのですが、主人公の少年はこのコロッケの肉を絶賛しています。なんていうか、普通のコロッケに使われている肉はちゃんとしていない肉だと少年は言うのです。肉を取った骨にもまだちょこっと筋だか肉だかわからないような部分がのこっていて、それを削ってミンチにしてそれをコロッケに使っているのだと言ってたような気がします。
だから他のコロッケはそんなすじ肉というかくず肉が使われているのであんまりなんだけど、ここのコロッケはそんなことをしてない。ちゃんとした肉を使ったコロッケなのでめちゃ美味い!
そんな感じの描写があったのです。
小さくて素直だった私は、ふんふんとそれを読み、そうなのかコロッケに入っているお肉っていうのはそんなお肉なんだ!と信じ込みました。
そして、ちゃんとしたお肉で作られたコロッケ。この少年がここまで絶賛するコロッケはどれほど美味しいのだろうと、口の中の唾をごくんと飲み込んでいたわけです。
ちょっと考えてみれば、家で出てくるコロッケはごくごく普通に売っているミンチを使って作られているわけで、逆にこんな骨をけずってつくったミンチで作ったコロッケって食べようと思ってもなかなか食べられるものではないのですが、小さかった私は多分母に、コロッケを作るときの肉について尋ねたような気がします。
記憶に残っているのって、ほぼこのコロッケについてだけなんですよね。
ここから小さい頃に読んだ本を割り出すことって可能なのでしょうか。
記憶だと絵本なのか児童文学なのかもあいまいです。
適当な語句で検索してみます。コロッケ、児童文学
かすかな記憶をたどるに、どうも絵本ではなかったような気がします。絵本よりちょっとすすんだ挿絵のある字の大きな本。いわゆる児童書とよばれるたぐいの本ではなかったのか。
コロッケと児童文学で検索をかけてみると、出てくるのが、
「コロッケ天使」ってやつなのですが、あらすじを読んでみた感じ、どうもこれではないような気がします。
「コロッケ先生」っていうのも「コロッケできました」ってのも違うっぽいです。
「コロッケ少年団」これはちょっと気になります。少年が主人公だったしなんとなく少年少女が出てきていたようなイメージがあります。しかし調べてもあらすじが出てきません。
こちらのページに行き当たり、「だぶだぶのだぶちゃん」という作品の可能性も出てきました。肉屋のコロッケというキーワードが出てきましたからね。
「こまったさんのコロッケ」は別の意味で懐かしいです。このシリーズ大好きでした。こまったさんともう一個シリーズがありましたよね?料理担当とお菓子担当に分かれていた記憶があります。
うーん、出てきません。
覚えている情報が少なすぎます。後覚えているのは少年が主人公ってくらいなので、検索語句に少年を足してみます。
そんなこんなで調べていると気になる題名が出てきました。
「コロッケ町のぼく」なんだか聞いたことがある気がします。
「コロッケ町のぼく」というタイトルが目にとまりました。
なんだか微妙に覚えがあるような気がします。これか!?これなのか?そう思ったのですが、出てきたのは本ではなくテレビドラマの情報です。

テレビドラマを見た記憶はさっぱりありません。
けれど、これを見る限り原作があるようです。筒井敬介という方が書いた同名の児童文学があるとのこと。
これなのか?と思ったので調べてみます。
コロッケ町のぼく の検索結果はテレビドラマばっかりです。
コロッケ町のぼくで検索をかけてみたのですが、
どれもこれもテレビドラマの解説ばかりで、児童文学についてはほとんど情報が得られません。
ドラマのあらすじも、

こちらにちらっと出てくるくらいです。
もうちょっと捜索を続けるとドラマのあらすじがもうちょっと詳しく書いてあるページにたどりつきました。
読んでいてもちっとも思い出せないなーと思いながら見ていたのですが、この中の第5回のハンス少年の話が頭のどこかをトントンしました。
そう言われると、堤防に穴が開いて水がちょろちょろと出てくるのを腕をつっこんでとめる少年の図が浮かんできます。
コロッケとかすかにこの図が結びついている気がします。
この本なの?私が求めているのはこの本なのかしら?記憶のかけらをたどっていくとどうもこの本のような気がするのですが、調べても調べてもコロッケのお肉について触れてくれているところに行き着きません。
コロッケ町のぼく はどこにある?
こうなったら読んでみるしかないと思ったのですが、
アマゾンで検索してもコロッケ町のぼくは出てこないのです。
じゃあ作者の筒井敬介で調べればいいのではっと思ったのですが、この筒井さんけっこう児童文学にかかわっていらっしゃるようで、日本世界の昔話系がずらずらっと出てきます。
ううむ、コロッケ町のぼくを読むにはどうしたら?と悩んだのですが、

同じようにこの本を探した人の質問にぶちあたったので手がかりが出てきました。
筒井敬介童話全集 第3巻 日曜日のパンツ
筒井 敬介〔著〕編集
フレーベル館
著者: 筒井 敬介〔著〕編集
出版:フレーベル館
サイズ:A5判 / 229p
ISBN:4-577-02118-8
発行年月:2000.7収録作品:
おばけロケット1ごう
コロッケ町のぼく
かいぞくでぶっちょん
日曜日のパンツ
「もめんのみみ」とおじいちゃんとぼく
雨ですてきなたんじょうび
おっしゃ!2000年出版ならまだチャンスはある!
と思って調べたら、
1983年年出版です。まあ品切れですよね。
ほしい本が絶版の場合、頼れるのは図書館です。
読みたいなと思った本が絶版になっていて売っていない場合、頼れるのは図書館という存在です。
古い本でも収集して保存してくれている可能性が高いです。ましてや児童文学系なら収集してくれている可能性はかなり高いと踏みました。
そして、図書館では自分のところにない本でも他の図書館から取り寄せてくれるというサービスがあります。
ということで、利用してみました。
「筒井敬介童話全集 第3巻 日曜日のパンツ」のおとりよせです!
自分でもなぜここまでコロッケにこだわっているのかよくわからなくなってきましたが、あのコロッケにもう一度会いたいなっと思ったのです。
10日くらいでおとりよせしてくれました。
幸い、同じ県内にこの本を所蔵している図書館があったようです。
お願いしてから10日くらいでしょうか。届いたという知らせが来たのでいそいそと取りにいってきました。
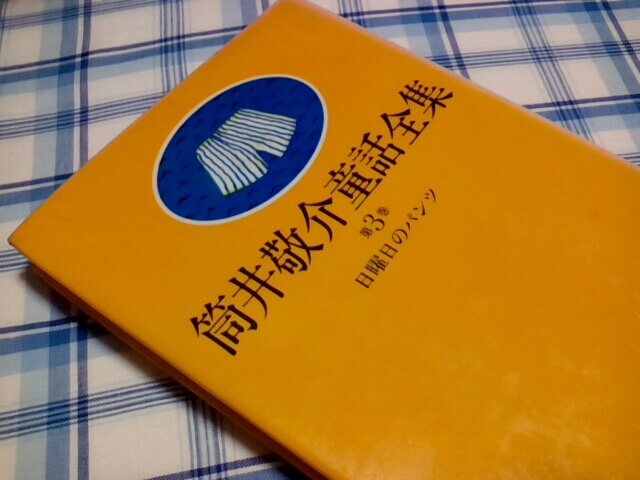
表題の「日曜日のパンツ」にはまったく覚えがありません。
でもこのタイトルのせいで少し恥ずかしい思いをしました。
「日曜日のパンツ」っていう本を取り寄せたいって頼まないといけなかったわけです。パンツの本をわざわざ取り寄せたわけですよ!
違うんです、私の目的はコロッケなんです!って聞かれてもいないのに弁明したい気持ちになりました。
目次を確認するとありました!「コロッケ町のぼく」です

よっしゃ!!とガッツポーズを決めました。
これを読みたかったわけです。はてさて、コロッケ描写はどうなっているのでしょうか?
結論から言えば私が読みたかったコロッケはこの「コロッケ町のぼく」のコロッケでした。
ありました。ありましたよ!コロッケ描写!
ただ、とてもびっくりしました。この「コロッケ町のぼく」という作品にとってさいたまやのコロッケの描写ってごくごく一部分なんです。
45pから114pまでがコロッケ町のぼくなので70pほどの作品です。
その中で私が読んだコロッケのお肉がくず肉じゃないっていう描写はほんのちょっとです。
それから、にくがいい。ほねそうじのにくじゃない。ほねそうじのにくなんて、だれも知るまいが、ぼくは食堂のひとりっ子だから知ってる。
にくやで、ほねへくっついているにく、というよりすじみたいなところを、小刀でごしごしけずりとる。これを、ひきにくのきかいにかける。すると、やすいひきにくができる。たいがいのにくやのコロッケには、これが入っている。だから、はとはの間にはさまってしまうんだ。
さいたまやのコロッケには、こんなにくは入ってない。
筒井敬介童話全集第3巻 57p より
こんなちょっぴりの描写を私はどれだけ執念深く覚えていたというのでしょうか。
いえ、ちゃんと他にもこのさいたまやのコロッケが美味しい理由は説明されているのです。値段が安くて(なんと25円です!)パン粉が手で持ってもこぼれなくて、色がカステラの上っかわみたいななんともいえないいい色で、しおあじがちょうどいいのです。
でも、私はこんな描写はほとんど覚えていませんでした。ひたすらコロッケの中に入っている肉について覚えていました。
とにかく、肉が美味いコロッケってところが私には魅力的だったんですよね。
読み返してみても内容はさっぱり覚えていませんでした。
あっ、ハンス少年が堤防の決壊を自分の手をつっこんで止めるエピソードはちゃんとありました。ここら辺だけはほんとうにちょこっと覚えています。
ただ、私の記憶だと主人公の少年がとめていたような気がしたので記憶が本当にあいまいになっているなーと思いました。
たどりつくまで、ちょっと大変でしたが、子どものころに読んだおいしそうなものにまた出会えて私は嬉しいです!
コロッケがめちゃくちゃ食べたくなりました。もちろんちゃんとした肉の入ったやつです!
最後に、この美味しいコロッケをつくっているさいたまやというお店はコロッケの油に引火して火事になって半分やけてしまってお話のラストではまだ営業再開の目処がたっていないことをお知らせします。
あのコロッケは物語の中でも食べられない幻のコロッケになってしまっていました。とても残念です。



